【囲碁】大人が二年半で五段になった話 EP1「強い人を真似しまくる」

こんにちは!ひかるです。
このシリーズでは僕自身の経験をもとに
皆さんの囲碁上達の参考になる内容を書いていこうと思います。
こんな悩みを解決できるかも
- 大人から囲碁をはじめたけど上達するのか不安
- 上達の壁に当たってしまいどうすればいいのかわからない
プロ修行なし!二年半で5段になった碁の環境

僕の囲碁の成り立ち、環境はこんな感じでした。
- 20歳を過ぎてから囲碁開始(ルールは子供の頃に)
- プロ修行なし
- 弱小囲碁部に所属
- 死活が苦手
囲碁の世界ではプロやプロに近い実力を持つためには子供の頃から碁の勉強をするのが当たり前。
そして大人になってからだと子供より吸収が遅い分大変だということがよく言われています。
それは事実でもあり否定することはありません。
・理由は単純で、大人は子供に比べ自由時間がかなり少ないですし、自分の価値観を変えにくい(頭が固くなる)からです。
では大人は強くなれないのでしょうか?
僕は二年半で五段になりました(現在7段)
これはかなり早いほうだと思います。
この5段という段位ですが、ゆるゆるのレーディングシステムではなく、当時プレイヤー数が一番多く基準が辛めだった「東洋囲碁」というネット碁での話です。
上記の通り、時間的にも環境的にもおそらくセンスもそこまで恵まれていませんでした。しかし、
プロ修行をするわけでもなく、自由時間も子供より圧倒的に少ない状態でも強くなることは出来ます。
そのために僕が考えていたポイントを以下に書いていきます。
囲碁が強い人と強くない人の違い
プロ修行を経験してる人ってかなり強いですよね。
直接知らなくても、なんだか強そうといった印象は受けると思います。
日本棋院にはプロの養成をする院生というシステムがあります。プロ修行と言えば
- 院生になる
- プロの道場に通う
- プロの弟子になる
というものが代表的です。
しかし大人になってからではこの方法は現実的ではないですね。
ではどうするか。
結局強い人は修行で何をしてそこまで至ったのか?
これを知ることが自身の上達の第一歩だと思います。
そして一言で言ってしまえば強い人は相当な量の勉強したということ。
強い人ほど勉強しているのはあたりまえですが、これにほぼ全て詰まってると思います!
そして多くの方がここで大変そうだ、やっぱり無理なんじゃ、と思う方も多いと思います。
確かに同じだけのことをやって同じだけの結果を出そうと思ったら大変ですよね。
だからこそ知っておいてほしいことがあります。
環境が違いすぎますから。
要は趣味で強くなりたい人向けに量を調整すればいいのです。
そしてもう一つ、上達の流れを把握しておきましょう。
勉強して強くなると必ずどこかで壁に当たります。
そこで投げやりになるとそれ以上は強くなりません。
勉強しては強くなり、また壁に当たり勉強するというサイクルを繰り返します。
これの理解があれば壁が中々超えられないときにモチベーションが続きやすいです!
※今後の記事で詳しく補足します
囲碁が強い人をひたすら真似しまくりました

僕に囲碁のセンスがあったかどうかはわかりません。
ただ急激に上達した過程を経験し、自信を持って伝えられる方法は
強い人の打ち方や価値観、勉強方法まで真似し続けた
というものです。
これがそのまま僕の見解です(笑)
 ひかる
ひかる僕は強い人に、ある問題集を1000周やったと聞いて自分も1000周やりました(笑)
そのほか基本死活辞典の暗記やそのほか棋書を読み漁ることになりました。
棋書に載っている図はくまなく並べ、ネット碁で実践してみることの繰り返しです。
ただこれは中々大変ですよね。
そこでもう一つおすすめの方法があります。
「継続的に」強い人に検討してもらうこと
これは頻度が高ければ高いほど効果的です!
自分の碁を見てもらい、うわ手の視点での甘い所を指摘してもらう方法がおすすめです。
そしてそれを「暫定的に正しいこと」として受け入れ、自分の価値観や判断を上書きしていきます。
こうすることで我流による癖が残ってしまうことを予防しました。
この修正を加え続けるサイクルによって、強い人の価値観に近づきます。
検討してくれる人をお探しの方は囲碁事業者紹介も覧ください。
エピソード2に続きます。
人気ブログランキング投票
(クリックで投票します。よろしくお願いします!)

囲碁ランキング
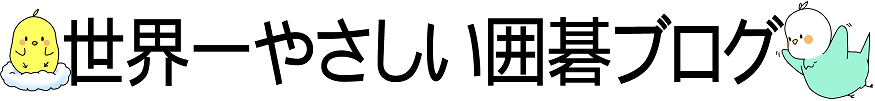









小学生と囲碁遊びをしています、と言うと、
子どもは上達が速いでしょう!って必ず言われますけど、
実はおとなと同じで、速い!子もいるし、ゆっくりの子もいます。
速い!特にものすごく速い!子が目立つので、そういう印象を受けるんですね。
だけど、ひとたび面白いと興味を持ち始めた途端に、
ぐいぐいと上達していくのは子どもによく見られます。
ひかる先生のおっしゃる通り、
興味があることに集中できる(興味ないことをほっぽっておける)
力と環境があるんだろうなと思います。
子どもだから上達できるということもないし、
おとなだから上達できないということもないですよね。
というわけで詰碁がんばります。
コメントありがとうございます!
りくのらさんのおっしゃる通り、興味が湧くかどうかで吸収力はかなり変わりますね!
それに類することを次のEP2(https://hikarugo.com/zyoutatu-ep2)に書いたので良かったら読んでください。
子供も大人も多少環境や条件に違いはあれど伸びしろはありますから、努力次第で上達は出来ますね!
詰碁ファイトです!
こんにちは。
2年半で5段になったお話面白かったです。
私は1年強で野狐9級で止まっているので、
新たな対策を模索しているところでございます。
ちなみに下の2つの記事で疑問があるのですが、ご教示頂けないでしょうか。
EP1「強い人を真似しまくる」
EP7「うわ手に互先で挑み続ける」
EP1の「強い人」というのは特定の方でしょか?
例えば囲碁インストラクターとかでしょうか?
一般の強い人が明らかに弱い人と対局する
(ましてや検討までする)メリットが無いので、
お金をかけて「強い人」に指導(?)
してもらえる環境を作られたのでしょうか?
(身内にいるとかなら分かりますが)
EP7の「うわ手」についですが、
顔も話したことも無い人にネット碁で
「した手ですが互先お願いできないでしょうか?
そして検討もしてください」
と頼まれていたのでしょうか?
EP1の質問と同様、うわ手にとってメリットが無い気がするので、
その頼みを聞いてもらえるイメージが湧きませんでした。
EP1,7のイメージがクリアになると
上達ヒントになりそうですので
ご教示頂けますと幸いです。