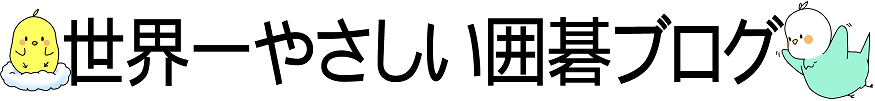AI検討解説Part4 河合将史先生と解説!後編【高段者向け】

こんにちは!ひかるです。
今回はPart3の続きです。
ぜひ続けて読んでみてくださいね!
どちらに打ち込む?途方もない部分を考察してみる
それでは実戦に戻ります。黒番。
こちらの場面では実戦Aの打ち込みに対し絶芸はBを示しました。
評価値は3%ほどの差しかありませんが、考察してみようと思います。
 ひかる
ひかる先生、AとBの違いについてですが思うことがあります。
Aに打ち込むと以下のあたりの白が固まることで黒△がより攻められやすくなる可能性がありますが…

 ひかる
ひかる仮にBの側へ打ち込んだとすれば、先ほどと比べて△から離れているので黒が攻められやすくはなりにくいのかと。

 河合先生
河合先生むずかしい場面だけど確かにその着眼点はあるかもしれないね。
 ひかる
ひかるしかし絶芸は白2を見てから一旦保留して左辺に打ち始めるんです。

 河合先生
河合先生へー!興味深いね。
フリカワリを含めた攻防が深い!
先程の図の続きを見てみましょう!
 ひかる
ひかる下辺への打ち込みを様子見として保留、その後左辺に打っていますね。
以下のときAのツケコシが気になりますがどうでしょうか?

 河合先生
河合先生それにはこのような図が想定されるけど、白はあまり狙いもないからさっきの図の方がいいかもしれないな。

 ひかる
ひかるなるほど!
一つ一つが繊細です。
 河合先生
河合先生以下のように2と受けるのは△のあたりとの連絡が薄いから打ちづらいね。

 ひかる
ひかるAIの示す応酬が相応のようですね。
AIではなく実戦の着手だけど
次はAIの手ではないですが参考になる打ち方を取り上げてみたいと思います。
※Aが実戦です
 ひかる
ひかる先生!この場面、一般的にはBと打ちそうな感じですが実戦はAと打ちました。
ここはどういった意図なのでしょうか?
 河合先生
河合先生ここは先手と後手の違いがポイントだね。
例えばBの進行だと…

 河合先生
河合先生ここで黒が先手になり、Aを睨みながら打たれてしまう。
白はそれをきらって先程の選択をしたということだね。
 ひかる
ひかるふむふむ!
 河合先生
河合先生実戦の進行を見てみると右辺で少し黒に地を与えることになるけど、先手で右上に着手しているから黒は案外大きくならないんだ。

 ひかる
ひかるですね!比較してみると白の打ちやすさがわかる気がします。なるほど~
どの場所が大きい?AIはどうする?
今回最後の検討図です。
常に大きい場所を見極め打ちまわす判断力は勉強になります!
※Bが絶芸の示す手
 ひかる
ひかる絶芸はBを利かしたのち上辺を重視していますね!
評価値は約10%の差があるのでハッキリBがよさそうですか。
 河合先生
河合先生そんなに違うんだ!
左辺と上辺ならはっきり上辺の方が良さそうだね。
 ひかる
ひかる白△も利かしてありますし落ち着いて考えればわかりそうな気もしますが、検討でも実戦でもAIの判断力は変わらない分、冷静で強いですよね。
勉強になります!

 河合先生
河合先生我々プロもこのような石の方向や強弱についてAIから学ぶことは多いと感じるね!
 ひかる
ひかるAIでの学びがどんどん一般化して碁のレベルも上がりそうですね!
今回はこの辺で終わりになります。河合先生ありがとうございましたー!
 河合先生
河合先生ありがとうございました。
囲碁AIの研究がみなさんの参考になることを願っています!
※この記事は日本棋院所属棋士の河合将史五段の監修のもと制作しています。
人気ブログランキング投票
(クリックで投票します。よろしくお願いします!)

囲碁ランキング